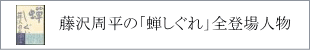 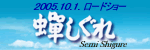 |
||||||||||||||||||||
牧 文四郎 |
まき ぶんしろう |
牧家の養子(初出15歳) 居駒塾 石栗道場 後に助左衛門を襲名 <郡奉行> |
||||||||||||||||||
| 牧 助左衛門 | まき すけざえもん | 文四郎の父 海坂藩 普請組 <28石 二人扶持> 寡黙 | ||||||||||||||||||
| 牧 登世 | まき とよ | 文四郎の母 叔母(実父の妹) | ||||||||||||||||||
| 牧 せつ | まき せつ | 文四郎の妻 岡崎亀次<25石 青苧蔵役>の次女 浅黒い十人並みの容貌 | ||||||||||||||||||
| 小柳 ふく | こやなぎ ふく | 甚兵衛の娘(初出12歳) 細くて黒目だけのような眼、小さな口元 後に藩主の寵愛を受ける側女に |
||||||||||||||||||
| 小柳 甚兵衛 | こやなぎ じんべい | ふくの父 牧家の隣家 普請組 <後に80石御蔵方に> | ||||||||||||||||||
| 小柳の女房 | こやばぎのにょうぼう | 肉の薄い平べったい顔 | ||||||||||||||||||
| 小和田 逸平 | おわだ いっぺい | 文四郎の親友(初出16歳) 居駒塾 石栗道場 <百石 漆原町> 10歳で跡目を継いで当主に、後、小姓組で出仕 |
||||||||||||||||||
| 小和田 琴代 | おわだ ことよ | 逸平の妻 漆原町 池内<勘定目付>の娘 | ||||||||||||||||||
| 島崎 与之助 | しまざき よのすけ | 蝋漆役<郷方回り>次男 居駒塾 石栗道場 居駒塾始まって以来の秀才 | ||||||||||||||||||
居駒 礼助 |
いこま れいすけ |
私塾・居駒塾頭 |
||||||||||||||||||
| 石栗 弥左衛門 | いしぐり やざえもん | 石栗道場主 物頭の家の嫡子 20歳で江戸詰めとなり空鈍流と出会う 18年の修業の後、国許で道場を開く |
||||||||||||||||||
| 弥左衛門の妻女 | やざえもんのさいじょ | 弥左衛門より10歳以上若い ふっくらした童顔 肌につや | ||||||||||||||||||
| 佐竹 金十郎 | さたけ きんじゅうろう | 石栗道場 師範代 <10石 御馬乗り役> | ||||||||||||||||||
| 丸岡 俊作 | まるおか しゅんさく | 石栗道場 次席 | ||||||||||||||||||
| 大橋 市之進 | おおはし いちのしん | 石栗道場 席次3番 <120石 家中 部屋住み> 23歳 | ||||||||||||||||||
| 塚原 甚之助 | つかはら じんのじょう | 石栗道場 席次4番 | ||||||||||||||||||
| 犬飼 兵馬 | いぬかい ひょうま | 石栗道場 犬飼家<300石 御使番>次男 父親が長く江戸屋敷で御留守居役 | ||||||||||||||||||
| 杉内 道蔵 | すぎうち みちぞう | 石栗道場 14歳 文四郎を慕う後輩 | ||||||||||||||||||
| 野田 弥助 | のだ やすけ | 石栗道場 席次6番 | ||||||||||||||||||
| 矢田 作之丞 | やだ さくのじょう | 石栗道場 席次5番 <100石 御納戸組> 温厚 吉村信蔵を切る | ||||||||||||||||||
| 矢田 淑江 | やだ よしえ | 作之丞の妻 やや目尻の吊った勝気そうな眼が黒く澄んで、美しい人 | ||||||||||||||||||
| 矢田の母 | やだのはは | 盲目 | ||||||||||||||||||
| 布施 鶴之助 | ふせ つるのすけ | 矢田淑江の弟 小野道場 <実家75石> | ||||||||||||||||||
小野 喜玄 |
おの きげん |
無外流 小野道場主 小柄 初老 半白の髪に長いあごひげ 眼光鋭い |
||||||||||||||||||
| 三宅 藤右衛門 | みやけ とうえもん | 小野道場 師範代 30半ばで鬢の毛が抜け上がっている | ||||||||||||||||||
| 石川 惣六 | いしかわ そうろく | 小野道場 文四郎より2・3年上 無口 | ||||||||||||||||||
吉村 信蔵 |
よしむら しんぞう |
松川道場の剣士 <御蔵方> 小舟町 不振な切り死 松之丞君派の連絡係 |
||||||||||||||||||
| 興津 新之丞 | おきつ しんのじょう | 松川道場 山吹町騎馬衆興津家四男 長身 | ||||||||||||||||||
| 新川 松三郎 | しんかわ まつさぶろう | 松川道場 熊野神社の奉納試合での犬飼兵馬の対戦相手 | ||||||||||||||||||
| 山根 清次郎 | やまね せいじろう | 居駒塾 松川道場 <230石 御徒歩頭 嫡男> 17歳 | ||||||||||||||||||
| 江森 利弥 | えもり としや | 居駒塾 山根のとりまき | ||||||||||||||||||
| 野瀬 郁之進 | のせ いくのしん | 未亡人となった矢田淑江を訪ねる男 <300石 御奏者番の嫡男> | ||||||||||||||||||
右京太夫正威 |
うきょうだゆうまさたけ |
先々代海坂藩主 |
||||||||||||||||||
| 亀三郎君 | きさぶろうぎみ | 志摩守 正室の子 | ||||||||||||||||||
| 松之丞君 | まつのじょうぎみ | 側室おふね様の子 | ||||||||||||||||||
| おふね様 | おふねさま | 藩主の側室 松之丞君の母 | ||||||||||||||||||
| おまん様 | おまんさま | 国許の側女 御城を束ねる実力者 | ||||||||||||||||||
| 栗栖 | くりす | 欅御殿に藩主の供をする男 <小姓組> 牡蠣のように口が固い | ||||||||||||||||||
| 柴原 研次郎 | しばはら けんじろう | 藩校の学監 (江戸葛西塾出身) | ||||||||||||||||||
| 遠山 牛之助 | とおやま うしのすけ | 中老 (江戸葛西塾出身) | ||||||||||||||||||
| 菰田 庄兵衛 | こもだ しょうべい | 番頭 (江戸葛西塾出身) | ||||||||||||||||||
| 相羽 惣六 | あいば そうろく | 奉行助役 声が大きい | ||||||||||||||||||
| 秋吉 玄蕃 | あきよし げんば | 月番家老 老人 | ||||||||||||||||||
| 葛西 蘭堂 | かさい らんどう | 江戸葛西塾 儒者 | ||||||||||||||||||
里村 左内 |
さとむら さない |
次席家老 小柄な老人 髪は真白 日焼けしたへちま顔 |
||||||||||||||||||
| 稲垣 忠兵衛 | いながき ちゅうべい | 元中老 名執政といわれたが数年前に引退 -里村派- | ||||||||||||||||||
| 遠藤 三郎太 | えんどう さぶろうた | 稲垣忠兵衛の近縁につながり <小姓組の古株> -里村派- | ||||||||||||||||||
| 村上 七郎右衛門 | むらかみ しちろうえもん | 助左衛門の介錯人 <小姓組〜馬廻組> 欅御殿襲撃の首魁 長身 | ||||||||||||||||||
| 探索の男 | たんさくのおとこ | 欅御殿襲撃一味の見届け役 物のように動かない男 | ||||||||||||||||||
平田 帯刀 |
ひらた たてわき |
前家老 政変後切腹 -横山派- |
||||||||||||||||||
| 兼松 熊之助 | かねまつ くまのすけ | 現中老 政変後領外追放 -横山派- | ||||||||||||||||||
| 横山 又助 | よこやま またすけ | 海坂藩 次席家老 50見当 福々しく太っている 頬も肩も丸く腹が出ている | ||||||||||||||||||
| 加治織部正 | かじおりべのしょう | 藩主の叔父 かつての名家老 50過ぎと見える 烏天狗のような風貌 代官町の奥の広大な屋敷「杉の森御殿」に住む 元石栗道場の高弟 |
||||||||||||||||||
| 磯貝 主計 | いそがい かずえ | 欅御殿の警護 中年の武士 | ||||||||||||||||||
| 北村 | きたむら | 欅御殿の警護 | ||||||||||||||||||
| おみちどの | おみちどの | 欅御殿の女 20過ぎほどに見える | ||||||||||||||||||
| 浅井 平三郎 | あさい へいざぶろう | 百石の加増で町奉行に抜擢 | ||||||||||||||||||
| 田宮 仲次郎 | たみや なかじろう | 藩主側近第一の権力者 <側用人> 家老も一目置く | ||||||||||||||||||
| 榊原 修理 | さかきばら しゅり | 新しい次席家老 40半ば | ||||||||||||||||||
| 堀江 勘十郎 | ほりえ かんじゅうろう | 組頭 40半ば | ||||||||||||||||||
樫村 弥助 |
かしむら やすけ |
助左衛門の直上司 <郡奉行> |
||||||||||||||||||
| 北野 | きたの | 文四郎の同僚 <郷方勤め> | ||||||||||||||||||
| 青木 孫蔵 | あおき まごぞう | 文四郎の先輩 <郷方勤め> 30半ば浅黒い顔 無口な男 | ||||||||||||||||||
| 菅井 甚八 | すがい じんぱち | 青木の後に暗殺される <馬廻組> -横山派- | ||||||||||||||||||
| 山崎 | やまざき | 〃 <小姓組> -横山派- | ||||||||||||||||||
| 藤次郎 | とうじろう | 金井村 <村役人> 40半ば 面長で品の良い顔立ち 助左衛門の助命嘆願をとりまとめた男 |
||||||||||||||||||
| 長之助 | ちょうのすけ | 金井村 <村役人> 背が高く太って丸顔 | ||||||||||||||||||
| 伊作 | いさく | 金井村 古口田地区の田圃の持ち主 背が低くて痩せている年寄り | ||||||||||||||||||
| 権六 | ごんろく | 金井村 船頭 夜目にも屈強な体つきがわかる大男 | ||||||||||||||||||
磯貝 四郎太 |
いそがい しろうた |
龍興寺での対面責任者 <御兵具役> |
||||||||||||||||||
| 関口 晋作の父 | せきぐちしんさくのちち | 龍興寺で藩の対応を批判 | ||||||||||||||||||
| 服部 市左衛門 | はっとり いちざえもん | 文四郎の実家の兄 <120石 右筆> 鷹匠町 | ||||||||||||||||||
| 弥助 | やすけ | 服部家の下男 | ||||||||||||||||||
| 嘉平 | かへい | 服部家奉公人 老人 | ||||||||||||||||||
| はる | はる | 服部家の使用人 | ||||||||||||||||||
| 石塚 半之丞 | いしづか はんのじょう | 牧の実家の姉の嫁ぎ先 | ||||||||||||||||||
| 石塚 季枝 | いしづか きえ | 文四郎の実家の姉 14歳で嫁ぐ | ||||||||||||||||||
| 山下 重助 | やました じゅうすけ | 普請組 牧家の隣家 | ||||||||||||||||||
| 宮浦の女房 | みやうらのにょうぼう | 小柳家の隣家 | ||||||||||||||||||
| 藤井 宗蔵 | ふじい むねぞう | 文四郎の烏帽子親 番頭 <300石> 小吹町 40前後 松川道場 20年前、直心流戸村道場で助左衛門と同門 |
||||||||||||||||||
| 一柳 弥市郎 | いちりゅう やいちろう | 助左衛門と同僚 切腹 | ||||||||||||||||||
| 尾形 久万喜 | おがた くまき | 大目付 顔も眼も丸く大きい大男 | ||||||||||||||||||
| 山岸の女房 | やまぎしのにょうぼう | 普請組屋敷 牧家の北隣 | ||||||||||||||||||
| 松永 | まつなが | 小柳家の後に組屋敷に入った | ||||||||||||||||||
| 石倉 駿蔵 | いしくら しゅんぞう | 文四郎にはなたれた刺客について密談 | ||||||||||||||||||
おきみ |
おきみ |
砧屋の酌とり |
||||||||||||||||||
| おとら | おとら | 砧屋の酌とり 小太り 色白 丸顔 | ||||||||||||||||||
| およし | およし | 砧屋の女中 | ||||||||||||||||||
| 幸太 | こうた | 布施の兄が淑江探索に連れて行った下男 | ||||||||||||||||||
| 上原の妻女 | うえはらのさいじょ | 文四郎母方の親戚 縁談を持ってくる | ||||||||||||||||||
| 久坂 | くさか | <郷目付> | ||||||||||||||||||
| よね | よね | 海坂藩江戸下屋敷の台所女中 欅御殿の情報元 | ||||||||||||||||||
| 砧屋の主の妾 | きぬたやのあるじのめかけ | 頬骨の高い厚化粧の女 | ||||||||||||||||||
| 桑村 | くわむら | 大浦郡矢尻村代官 | ||||||||||||||||||
| 中山 茂十郎 | なかやま もじゅうろう | 矢尻村代官手代 | ||||||||||||||||||
| 徳助 | とくすけ | 矢尻村 代官屋敷の下男 | ||||||||||||||||||
| 三国屋番頭 | みくにやばんとう | 代官所にお福様の使い 中年の男 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
<<< 戻る <<<
